

|
(このお話の前半はこちら)
●雪は横から吹いてくる
それと、本の中にもたくさん書きましたが、本当に厳しい自然のこと。
最近はゆるくなりましたけども30年、40年前というのは、
北海道の田舎っていうのは、もうね、冬なんていうのは、
ここでいったいどうやって人が生きているんだろうっていうような。
とんでもなく風が強くて、雪が上から降ってくるんではなくて、
ものすごく風が強いものですから雪が横から来るんですよね。
ということは、顔を隠して体を斜めにしていないと、
息ができないし半身が雪だらけになっちゃう。
でもそれはね、厳しかったからよけいに覚えていられるし、
とっても貴重な経験をしたから、今でもよかったと思っているんです。
アラスカ行ったことのある友人が遠別へ行って、
「本当にここ、アラスカみたいだね」って言われたのは
気持ち的に複雑でした。緯度としては稚内なんて、
パリとかニューヨークとかと変わりないはずなのに、
アラスカみたいっていわれたのは、ちょっと、かなりショックでしたね。
それはアラスカ悪いってわけじゃあないんですけどね(笑)
あと、本当にマイナスの要素でしかなかった風の強さですが、
日本では北海道のうちのあたりの一部と、沖縄の一部が
日本でいちばん風の強い場所のようです。
でも今はその風を利用して、風力発電として
風車を立てているんです。
丘のうえに20機、30機と並んでいまして、
1機がオランダ製で何千万とするやつなんですけど、
それで、近隣の電力は十分まかなえるという規模なんですが、
それをはじめて見たときは、
何が立っているんだかさっぱりわからなくて、
風景が変わっちゃったなと思った。
でも、昔は、なーんの使い道もなかった強い風が、
そういうものに使われているっていうのは、
時代が進歩したなあって……実感させられましたよね。
●口伝えに話を聞く
それから、いちばん最後に父親の戦争体験みたいのが書いてあります。
シベリアに抑留されちゃった、2年間くらいの話なんですが、
まさに今日のテーマである、家族の歴史みたいなもの。
それは、昔、テレビが入る前っていうのは、
(小学校5年の終わりにテレビがうちに来たんですけども、)
その前っていうのは、
やっぱりストーブがあって、そのまわりで、
親の会話、ばあちゃんと母親の会話、
ばあちゃんと父親、もしくは近所のおばさんとか、
いろんな人たちがストーブの周りに集まってきて、
漬物をかじりながらお茶を飲んでいる話を、
自分は…子どもはね、外れたところにいるんですよ、でも、聞いている。
さっき言った、子どもは観察者だというのは
そういうことで言ったんですけども、
そうやって、飛び飛びながらでも聞いている話が
ものすごくこう、深く自分の中に突き刺さっていて、
それがしっかりした記憶になって残っていました。
父親の戦争の話も、子どものいる前ではしないんですね。
それが、戦友が父を訪ねてきてお酒を酌み交わしているときに、
酔ってくると出てきた話を
隣の部屋でこう、ふすまを開けた状態にして聞いていたという、
まあ、そういう記憶があります。
で、それをもとにして、書いた話が結構な量になりまして、
ずいぶん、聞いてたんだなあって思いました。
そのときに父がしゃべっていたように……まあ口語体で書いたほうが
伝わりやすいだろうと思ってそう書いたんですけども、
それを母親に確認しながら書いていると、
その時代に、もし自分が父親の時代に生まれて戦争に行ってたら
同じ体験をするかもしれない、
でもたまたま父親がその時代を体験するはめになった。
で、父親が今の時代にもし自分の年齢だったら
この時代を、生活を楽しんで生きていられたかもしれない。
たったそれだけのことかもしれないんだけれども、
その時代に生きたという事実を、どういう風にかでも……
形が少し変化してもいいから、
次の時代へ伝えるということを、ちょっとやりたかったんですね。
ですから、すごい怖い話も、人を殺すという話も含めて、
本当にこう……聞かされました。
それを、じゃあ今は自分の子どもに話をしていたかというと、
それができないから活字にした、みたいなところがあります。
いまと違って昔は本当に、口伝えに聞く話なんてのは
東北なんかでもよくある、昔話をするっていう、
そういう良さっていうのがあったんですが、
今の情報っていうのは、もう、耳と目で両方からワッと来ますから、
もう、それに翻弄されちゃうっていうところがあると思うんですけれども、
聞くだけの話、見るだけの話っていうのは、
それだけで想像力を鍛えるところがあると思う。
●私の書いた本たち
今の情報の入り方がいいのかっていうと、よくわかりません。
ですから、いま、いちおうマックを使って原稿は書けるんですが、
メールはできません。
できないということを取り柄にしようかなあと
思っているところがあります(笑)
というのは、できると、自分が発信するし、向こうからも来るっていうことは、その面倒くさい波に飲まれてしまうだろうなと思うと、
自分は使わないでおこうと。
あくまでも手紙でいこうと考えています。
そういう話を雑誌に書いたら、ある出版社から、
「捨てられない手紙の書き方」っていうのを書きませんかという話が来て、
「なるほどなー」と思っていま書いているところなんですよ。
それは形式ばらずに自分の思うことを素直に出す手紙が
いちばんいいんですよという本です。
それから、宣伝になって申し訳ないんですけど、
TOTO出版っていうところから、『光の家具、照明』っていう本を
つい最近、7月に出したんです。
それは30歳のとき始めてニューヨークに行ったときに、
個人の自宅に招かれまして、一週間いたんですけど、
そのときに見た光の体験がもとになっていまして、
シェードランプっていうランプがあるんですが、
それをもっと活用して豊かな明かりの生活をしましょう、
っていう提案です。
いつも蛍光灯で、仕事でも蛍光灯、帰っても蛍光灯では疲れませんか?
っていうことを書いた本です。
もう少し前の本には、『写真生活』っていう本もあります。
昔、写真ギャラリーをやっていたんですが、
写真とかを額装して家に飾りましょう、
そうすることによって、もっとそこのスペースというか空間が、
自分たちの空間になりますよ、って。
犬でいえば、電柱におしっこする、マーキングするっていうか、
それは犬が自分の存在を示す行為なんですが、
日本の今の家では澄む人の存在感や個性がとても薄いですから、
もっと自分らしさを家とか壁に反映させてもいいんじゃないですか?
っていう提案です。
●不思議なおじさんになりたくて
そうやって、何で本の装丁なんてしてる人が
こういろんな本を書いているかっていうと、
いろんなことに興味があるからなんです。
興味があるということは、少年のときからもう、ちっちゃな胞子が、
興味の胞子が、たくさん出ていた。
それをたくさんある引き出しの中にしまっておいた。
で10年20年たって、えさを隠したリスがどこに隠したのか
忘れていたみたいにずっと忘れていて、
どこになにをしまったか覚えていないんですけど、
引き出しを引っ張ったら、中でけっこう大きなものになっていた。
その何かをおじさんになって、かたちにしてみたい。
それが、読んでくれているひとに面白がられたい。ていうか、
そうですね、好奇心の強い大人を増やしたい。
そのために自分が何か役に立たないだろうかと、
ひそかに思ってたわけです。
女性たちはバイタリティと好奇心、この二大要素で生きていますから。
このふたつは男性は絶対にかなわないですよ。
で、おじさんは保守的です。
どうしても何をやるにしても女性が先で引っ張られると
ついていくのが男性です。
これが日本の男性の世界だと思うんですが……
日本のおばさんたちには、もっともっとこう、
企業に利用されることなく、自分の楽しみを前に出して、
どんどん人生を楽しんでほしい、
思い出作りをしてほしいなあという気持ちがすごいある。
で、そのために男の自分もね。
たとえばイタリアなんか行きますと、おじさんがオシャレなんですよ。
それと、おじさんがおしゃべり。
道を通るときにさっき話していたおじさんが、引き返すときにも
まだ話し込んでいる、
オバサン的なおじさん、なんかこう、そういうおじさんはいいなあと。
何かとこう「おじさん」が槍玉にあがりますが、
日本にももっと、開き直ったおじさんがたくさん増えてほしいなあ
って思ってまして、
そのエールを送る意味での僕自身の目標は、
「不思議なおじさん」になること。
たとえば「変なおじさん」っていってもいいんですけど。
それがまた、話はちょっとズレますが、
子どもたちが外で遊んでいるときに、
昔は近所のお兄ちゃんとか、影響を与えてくれる年上の人がいましたが、
で、もうちょっと成長すると、おじさんという人たち……
まあ血のつながった親戚のおじさんという人もいますが、
近所のおもしろいおじさんが与えてくれた影響力というのは、
結構こう大人になってからでも響いていまして、
私もそういうおじさんになってみたいものだというのがすごくあります。
●「おじさんは、お前を見てて感じたことがある。それ言ってもいいか」
息子が大学を受ける受けないって時に、
中学の時から遊びに来ている友達の男の子がいまして、
180センチくらいあってひょろひょろと背は高いんだけども、
そいつに
「大学どうすんの?」
ってきいたら、まだ何にも決めてないって。
で、何にも決めてないってどういうことよっていったら
「嫌でも大学くらい、いくんじゃないすか?」
他人事なんだよね。
で、そんときに
「おじさんは、お前を見てて感じたことがある。それ言ってもいいか」
「あー、いいっスよ」
「お前は昔からなんか物を作って、おじさんに
これおもしろいでしょう? っていっておじさんに見せにきてたのを
すごく覚えてるんだ。
そういうことを大人になってもやりたいという気があるか?」
って聞いたんですけども、そしたら、
やってみたいっていうんですね。
そういうのはプロダクトデザインっていって、
美大を出て、そういう会社に入らないと
その世界には行けないんだよ、
美大に入るには、いまお前、デッサンっていうものをやったことないだろ、
デッサンをするためには予備校に入る必要があって、
それにはお金がかかるんだけれども……ちょっとそれ、
おかあさんにきいてみイ?
で、次の日、その子のお母さんから電話があって、
「息子から話を聞きました、
ホントに親というものは、そばにいながら、
いちばん子どものことはわけがわかってない。
坂川さんが、ずっとうちの子を観察されてきた中で
そうおっしゃるんでしたら、たぶんそうなんでしょう。
私たちは、じゃあ、アルバイトしてでもなんでも
そのお金を出すように努力しますから」
っておっしゃって、
こちらも電話口でジーンと感動していたんですけどね。
そうやってその子は、その道の方向へ入っていくことになりましてね、
ただ、映画のようにはうまくいかなくて、
その年の入試は、デッサンなんてやったことがないんですから
美大の受験はすべておちました。
当然なんです。で、一年浪人してデッサンの予備校に行き、
次の年に受けましたが、大きいところは軒並み落ちました。
最後に新潟の長岡工業大学ってとこがありまして、
そこのプロダクトデザイン科に唯一受かりました。
予備校に行ってた時からそいつはユニークだっていうことは
予備校の先生からも聞いていたんですが、
彼は、いまは学年でかなりいい成績を残しているって言うのを聞いて、ね。
その彼が、卒業して日本で小さくまとまるよりは、
ヨーロッパに出たほうがもっと能力を発揮するだろうなっていう
気はしているんですね。
で、その彼が息子のところへ遊びにきた時に、一応言っておいたのが、
お前の人生を決めたのはおじさんだからな(笑)
これ忘れないように、って(笑)。
●芯の部分でつながっていれば、大丈夫
そうやって子どもを見ていてあげる大人と、
大人を見ている子ども、という「バランス」を、
どう取るかっていうのがいちばん面白いことであり、
大事なことかなっていう気がしますね。
ですから、嘘も方便っていうのがありますけど、
子どもに関してはある程度の年齢にきたら嘘だろうが本当だろうが、
もう全部ばれてますね。
ただ、ばれてても、なんていうかな、いいんだ! っていう、
芯の部分でつながってるんだっていうことを意識していれば、
今ある形がすこしもめても、たぶん時間がたつと、
仲直りできるという気がしますから、ぜんぜん気になりません。
その
「気にならないという元になっている自信はなんですか?」
ときかれると、
自分で思い出すのは17歳のときに子どもを連れて行ったときの、
リアルな自分の姿なんですね。
それはもう、カッコウつけるんではない姿を見せたっていうことで、
子どもたちはもうレッテルを貼っているわけですよ、
父親に対して「あのくらいだな」的なレッテルというのを。
それで十分だと思います。
それがあるから、どうなっても多分大丈夫だという気がします。
だから親としてはもう、これから大人になった子供たちと
一緒に旅行することは、多分ないでしょう。
だからそういう意味では本当にみなさんにお勧めだし、
自分もいいことしたなって思っています。
15歳くらいでもぜんぜんかまわないですが、
ま、女の子なんかだと、お父さんの靴下なんか
割りバシではさんで洗濯機にもってっちゃうような時期にこそ
やるべきだと思います。
☆質問コーナー
Q. その旅行へ行かれたときの実際のエピソードを聞かせて下さい。
娘がバスタオル巻いて浴室から出てきたときに、
父親がどんな顔していればいいのかっていうのはまあ、
ちょっとあるわけですよ。
自分は兄弟が男兄弟で育ってきましたから、
女の子っていうのは慣れてない。
だからたとえば娘がうちで風呂に入っていて
ドアがすこしくらいあいていたとしますよ、
浴室の着替えするところがすこしこう明かりがついていたとして、
スッと父親がそこを通ったときに、
見てはいけないものを見てしまった感じがするわけですよ、
それはドキドキするんですが……妻だとそういうことはないですね(笑)
娘だと特別なんですよね。
ただそこで、本当にドキドキしたままで終わってしまうと、
娘が異性に変化してしまう。
そこで娘が風呂から出てきたときに、
「ここ閉めとけよな、
おとうさんドキドキするだろ」
って言い換えないと、
いつもの親子関係に戻れない気がする。
それと同じことがニューヨーク行ったときもありましたし。
あと、そうですね、私が30歳のときにニューヨークへ
初めて行った時の話ですが。
2日か3日、帰るのが遅れそうだと
国際電話を自分のうちにかけたんですよ。
そんときは娘が生まれて1年たってないくらいで
水疱瘡だったんですよ。
電話して、「遅れそう」って言ったら妻が
「もう水疱瘡で大変なんだから早く帰ってきて」
「わかったわかった」
って言ってた時期なんです。
それから17年後に、同じニューヨークのその電話をかけてたお店、
レストランみたいなところなんですけど、
そこに、娘とふたりで行ったわけです。
で、「ここからお前が水疱瘡だったときに、おとうさん電話したんだよ」
って。ま、父は感慨深いものがあるわけです。
そういう時間の共有、もしくは時間がたっているという思いを
話せるっていうことが、娘にとっても、
ここに父親と一緒に来たっていうことと同時に、
もうひとつ、17年前自分では記憶がないけれど、
自分が水疱瘡のときに若かったおとうさんはここから電話して…
っていうふたつのことが重なって、思い出せるわけでしょ。
そういう意味ではとても面白かったですね。
あとはもう、むちゃくちゃです。
お前が話せ、とか。お前のほうが英語知ってるだろとか、
自分が好きな化粧品があったりすると、
父親おいてけぼりでどっかスッと消えちゃうとか、
もうめちゃくちゃでしたね。
そうそう、かなり、情けない。
その情けないところを見せているのが、いいんですよ。
「一円だまの父親を見せる」
つまり、それ以上崩れない。
これが底辺だよと。
それが見えていればあとはいいことしかないんですから。
それを、オレは父親だとか、母親だっていうふうに、
はじめから垣根を作るから、
親はテーブルの向こう側にいることになっちゃって、
その距離感がなかなか埋められないんですよ。
たぶんね、親は背中を見せたほうがいいんですよ。
子どもが両親の背中から読み取ると思う。
ところが、子どもの前に向かっていると、どうしてもお仕着せになって、
その「1回」に少しでもいい例を見せようというのは、
おそらく親心だと思うんですが、
そのとき、親のほうから何かを出すこともいいんですが、
子どもから引っ張り出すということも両方やって、
初めてバランスがとれるのかな、ていう気はしています。
Q. 『遠別少年』には少年時代のことが鮮明に描かれていますが、
記憶力がとてもいいんですね。
昨日食べたものはすぐ忘れるんですけど、
小学校5年生くらいから高校生くらいまでのことは
ひしひしと、はっきりと、なぜか覚えているんですよね。
ここだけは記憶装置に刻み込まれているんで忘れないんですが、
それ以外は全然ダメなんです。
あと、匂いのこととかも好きなので、
匂いというのは記憶と密接に結びついているぶんだけ、
それを嗅ぐと……たとえば本のにおい、草のにおい、
いろんな匂いでフラッシュバックがぱーっと起こるんですね。
その記憶からまた別の記憶が引き出されるという。
まあ、私のたまたまの特技じゃないですかね。
ある作家の女の人が
『遠別少年』についてね、
「少年少女時代に味わっておかなくてはいけないこと全てが書かれている」
って書いてくれて、
それはとっても嬉しくてありがたいことばだったんです。
体験しなくても体験したように書くとか、味わえるとか、
そういうことは、人間としては子どもの時期の普遍性みたいなもの、
20年たっても50年たっても100年たっても同じような……
そっくり同じじゃあないけど
似たような感覚、情緒を味わうということがあるのだと。
逆のぼって過去であっても100年前の人でも
たぶん同じようなことがおきたら
同じようなことを感じるだろうな、って気がしてる。
それが書けたっていうことは、
自分の少年時代のことを練って練っているうちに残ったものを書いたから
そうなったと思うんですよ。
そうじゃなければ、少年の、あだ名で呼び合っていろいろ遊んだ友人との
ことだけで終わっちゃうと思うんですが、
それをどんどん削っていったときに残ったものが
遠別少年のエッセンスだと思うんですよね。
だから、自然に囲まれて育ったということが
とてもいい思い出を刻めたことだと。
都会で育った人にはそれなりのものがあると思うんですが、
奥行きがちょっとね、やっぱり。
それでいうと関西出身……こてこての大阪人がここにいたとするでしょ、
そうするとね、簡単に負けちゃうんですよ。
それはなにかっていうと、人間の濃さの違い。
人にもまれてもまれてもう、微妙にこういろんなところまで
自分を押し倒せるくらいのこてこてさは、
都会で育っているから持っているものであって、
逆に北海道みたいな自然の多いところの人は、弱いんですよ、
人間が。
自然には強いけれども人間に弱い。
人間が弱いから、みんなで集まって何かをしなければやっていけない。
『刑事ジョン・ブック』っていう映画、あれに出てくるシェーカー教徒、
そのひとたちはみんなで家を組み立てるんですが、
それって北海道では昔みんなそういうふうにしていたんですよ、
そうしないと生きて行けないから。
でも、それは人々が協力しあうという美しい部分でしかなくて、
その美しさが、深みにはまっていくと、なれなれしさになってしまって、
それがいいことかっていうと、私は決して好きではない。
でも、大阪人は別なんですよ。
だからどっかでうらやましいんだけど、
どっかで違っててよかったっていう、なんか不思議な気持ちがあるんです。
ここに関西のひといたら申し訳ないんですが…(笑)
でも、私の妻はなぜか関西なんです。
|
|


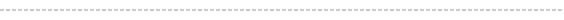



坂川栄治(さかがわ・えいじ)1952年北海道天塩郡遠別町に生まれる。雑誌「SWITCH」のアートディレクターを創刊から4年間つとめた。1993年、講談社出版文化賞ブックデザイン賞を受賞。現在までに装丁を手がけた本は2800冊を超える。著書に『写真生活』(晶文社刊)がある。

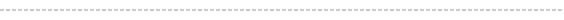

|

